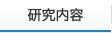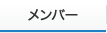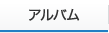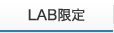ご挨拶
 当講座は、1877年の東京大学創立時に、理学部生物学科動物学教室として設置され、日本における生物学分野の先端研究と人材育成を担ってきました。以来、世界初の膜電位計測の成功、筋収縮におけるカルシウム要求性の発見、繊毛・鞭毛運動の構造・作動原理の解明など、独創的かつ先駆的な研究成果を世界へと発信し続けるとともに、動物生理学研究を推進する人材を多数輩出してきました。
当講座は、1877年の東京大学創立時に、理学部生物学科動物学教室として設置され、日本における生物学分野の先端研究と人材育成を担ってきました。以来、世界初の膜電位計測の成功、筋収縮におけるカルシウム要求性の発見、繊毛・鞭毛運動の構造・作動原理の解明など、独創的かつ先駆的な研究成果を世界へと発信し続けるとともに、動物生理学研究を推進する人材を多数輩出してきました。
初代のエドワード・モース教授から約140年のときを経て、2013年4月から榎本和生が第10代教授として講座を担当することになりました。講座名を脳機能学と改め、個性を生み出す脳神経回路の構築原理と機能原理の理解を中心課題として研究を推進します。
略歴
- 1997年 3月
- 東京大学大学院薬学系研究科 博士課程修了(井上 圭三教授)
- 1997年 4月
- 東京都臨床医学総合研究所 研究員(梅田 真郷室長)
- 2002年 5月
- カリフォルニア大学サンフランシスコ校 客員研究員(Yuh-Nung Jan教授、Lily Jan教授)
- 2006年 5月
- 国立遺伝学研究所 独立准教授
- 2010年 4月
- 大阪バイオサイエンス研究所 研究部長
- 2013年 4月
- 東京大学大学院理学系研究科 教授
- 2016年 7月
- 新学術領域研究「スクラップ&ビルドによる脳機能の動的制御」領域代表
- 2017年10月
- 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)「ニューロインテリジェンス国際研究機構」副拠点長
- 2021年10月
- AMED-CREST 早期ライフ領域「痛覚感受性の組織発達制御メカニズムの包括的理解と新規研究プラットフォーム創出を目指した研究」研究代表者
- 2023年10月
- 日本学術会議 第26期連携会員
受賞
- 2006年
- 日本生化学会 奨励賞
- 2008年
- 文部科学大臣表彰 若手科学者賞
- 2013年
- 第28回 塚原仲晃記念賞(ブレインサイエンス振興財団)
- 2018年
- 第7回 テルモ財団賞(テルモ生命科学芸術財団)
主要論文
1. Yoshino J, Mali S, Williams CR, Morita T, Emerson C, Emerson C, Arp C, Miller S, Yin C, Hemmi C, Motoyoshi M, Ishii K, *Bautista D, *Emoto K & *Parrish JZ
Drosophila epidermal cells are intrinsically mechanosensitive and modulate nociceptive behavior outputs.
eLife (2024).
2. Furusawa K, Ishii K, Tsuji M, Tokumitsu N, Hasegawa E & *Emoto K
Presynaptic Ube3a E3 ligase promotes synapse elimination through downregulation of BMP signaling.
Science 381: 1197-1205 (2023).
DOI: 10.1126/science.ade8978
3. Tsuji M, Nishizuka Y & *Emoto K
Threat gates visual aversion via theta activity in Tachykinergic neurons.
Nature Communications 14: 3987 (2023).
DOI: 10.1038/s41467-023-39667-z
4. Nakamizo-Dojo M, Ishii K, Yoshino J, Tsuji M & *Emoto K
Descending GABAergic pathway links brain sugar-sensing to peripheral nociceptive gating.
Nature Communications 14: 6515 (2023).
DOI: 10.1038/s41467-023-42202-9
5. Yoshino J, Morikawa R, Hasegawa E & *Emoto K
Neural circuitry that evokes escape behavior upon activation of nociceptive sensory neurons in Drosophila larvae.
Current Biology 27: 2499-2504 (2017).
DOI: 10.1016/j.cub.2017.06.068
6. Yasunaga K, Tezuka A, Ishikawa N, Dairyo Y, Togashi K, Koizumi H & *Emoto K
Adult Drosophila sensory neurons specify dendrite territories independently of dendritic contacts through the Wnt5-Drl signaling pathway.
Genes & Development 29: 1763-1775 (2015).
DOI: 10.1101/gad.262592.115
7. Kanamori T, Yoshino J, Yasunaga K, Dairyo Y & *Emoto K
Local endocytosis triggers dendritic thinning and pruning in Drosophila sensory neurons.
Nature Communications 6: 6515 (2015).
DOI: 10.1038/ncomms7515
8. Kanamori T, Kanai M, Dairyo Y, Yasunaga K, Morikawa R & *Emoto K
Compartmentalized calcium transients trigger dendrite pruning in Drosophila sensory neurons.
Science 340: 1475-1478 (2013).
DOI: 10.1126/science.1234879
9. Sakurai A, Koganazawa M, Yasunaga K, Emoto K & *Yamamoto D
Select interneuron clusters determine female choosiness in Drosophila.
Nature Communications 4: 1825 (2013).
DOI: 10.1038/ncomms2837
10. Morikawa R, Kanamori T, Yasunaga K & *Emoto K
Different levels of the TRIM protein Asap regulate distinct axonal projections of Drosophila sensory neurons.
Proc Natl Acad Sci USA 108: 19389-19394 (2011).
DOI: 10.1073/pnas.1109843108
11. Yasunaga K, Kanamori T, Morikawa R, Suzuki E & *Emoto K
Dendrite reshaping of adult Drosophila sensory neurons requires matrix metalloproteinase- mediated modification of the basement membranes.
Developmental Cell 18: 621-632 (2010).
DOI: 10.1016/j.devcel.2010.02.010
12. Koike-Kumagai M, Yasunaga K, Morikawa R, Kanamori T & *Emoto K
The target of rapamycin complex 2 controls dendritic tiling of Drosophila sensory neurons through the Tricornered kinase signaling pathway.
EMBO Journal 28: 3879-3892 (2009).
DOI: 10.1038/emboj.2009.312
13. Soba P, Zhu S, Emoto K, Younger S, Yang SJ, Yu HH, Lee T, Jan LY & *Jan YN
Drosophila sensory neurons require Dscam for dendrite self-avoidance and proper dendritic organization.
Neuron 54: 403-416 (2007).
DOI: 10.1016/j.neuron.2007.03.029
14. Parrish JZ, Emoto K, Jan LY & *Jan YN
Polycomb genes interact with the tumor suppressor hippo and warts in the maintenance of Drosophila sensory neuron dendrites.
Genes & Development 21: 956-972 (2007).
DOI: 10.1101/gad.1514507
15. Emoto K, Parrish JZ, Jan LY & *Jan YN
The tumour suppressor Hippo acts with the NDR kinases sin dendritic tiling and maintenance.
Nature 443: 210-213 (2006).
DOI: 10.1038/nature05090
16. Emoto K, He Y, Ye B, Grueber WB, Adler PN, Jan LY & *Jan YN
Control of dendritic branching and tiling by the Tricornered-kinase/Furry signaling pathway in Drosophila sensory neurons.
Cell 119: 245-256 (2004).
DOI: 10.1016/j.cell.2004.09.036
17. Emoto K & *Umeda M
An essential role for a membrane phospholipid in cytokinesis: Regulation of contractile ring disassembly by redistribution of phosphatidylethanolamine.
J Cell Biol 149: 1215-1224 (2000).
18. Emoto K, Kuge O, Nishijima M & *Umeda M
Isolation of a Chinese hamster ovary cell mutant defective in intramitochondrial transport of phosphatidylserine.
Proc Natl Acad Sci USA 96: 12400-12405 (1999).
19. Emoto K, Kobayashi T, Yamaji A, Aizawa H, Yahara I, Inoue K & *Umeda M
Redistribution of phosphatidylethanolamine at the cleavage furrow of dividing cells during cytokinesis.
Proc Natl Acad Sci USA 93: 12867-12872 (1996).
連絡先
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 脳機能学研究室
(理学部2号館151室)
TEL & FAX : 03-5841-4426
Email : emoto[at]bs.s.u-tokyo.ac.jp([at]を@に置き換えて送信してください)
研究室沿革
- 1877年
- 明治政府により東京大学が創立され、同時に理学部生物学科が設置される。動物学・生理学初代教授としてエドワード・モースが着任。大森貝塚の発見などを行う。
- 1979年
- モース教授の後任としてチャールズ・ホイットマン教授が着任。
- 1881年
- 箕作佳吉教授が着任。三崎臨界実験所の設立、動物学会の再編など、日本の動物学研究を支える体制整備に尽力した。
- 1909年
- 五島清太郎教授が着任。
- 1922年
- 谷津直秀教授が着任。従来の記載と比較よりも、分析と実証を重視する研究姿勢を示し、日本の動物学の中心を形態学・博物学から実験生理学へ移した。
- 1943年
- 鎌田武雄教授が着任。筋収縮におけるカルシウム要求性の発見や、世界に先駆けて膜電位の測定に成功するなど輝かしい研究成果をあげる。
- 1952年
- 木下治雄教授が着任。骨格筋細胞,繊毛虫類,魚類の色素胞,ムラサキイガイの繊毛細胞などをもちいて,主として興奮生理学的研究を展開する。
- 1972年
- 高橋景一教授が着任。鞭毛・繊毛の運動機構について生化学的研究や力学的研究など多彩かつ先駆的な研究を展開する。
- 1992年
- 神谷律教授が着任。繊毛の構造・機能について、分子遺伝学、生化学、組織学を駆使した多角的な先端研究を展開する。
- 2013年
- 榎本和生が第10代教授に就任する。教室名を脳機能学講座に改名し、脳神経回路の構築原理と作動原理を中心研究課題とする。