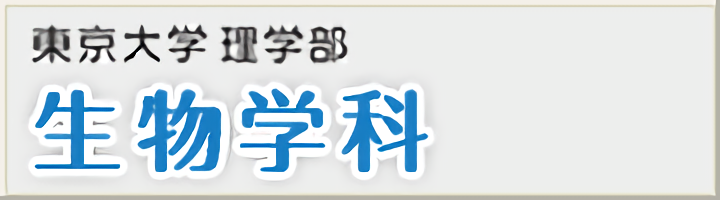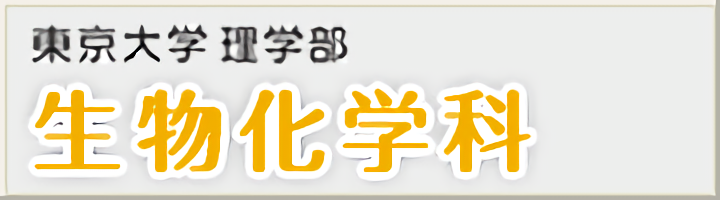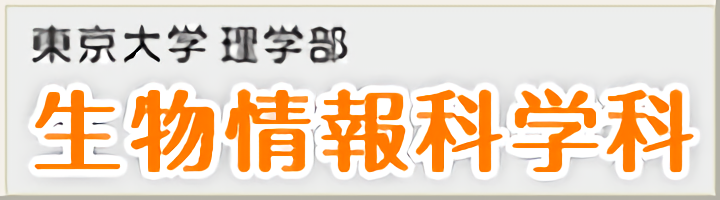黒田研公開ラボセミナー
完全変態昆虫における臨界サイズの適応的意義
廣中 謙一 博士(大阪大学理学研究科生物科学専攻)
2018年01月18日(木) 17:00-18:30 理学部3号館 310号室
本セミナーでは最適制御理論を用いて個体発生を理解する取り組みについて紹介する。
完全変態昆虫の幼虫は、ある臨界サイズを通過すると、変態する(蛹になる)ことが不可逆的に決定される。臨界サイズに到達した幼虫は、餌の有無にかかわらず一定時間後にステロイドホルモンを分泌し、変態を開始する。臨界サイズとステロイドホルモン分泌の間を繋ぐ遺伝的理解が進む一方で、そもそも「なぜ昆虫が臨界サイズを持つのか」という適応的意義については明らかではない。我々はこの疑問に答えるべく、幼虫組織と成虫組織へのエネルギー配分最適化という観点に立ち、理論と実験の両面から研究を進めている。
まず、臨界サイズを先験的に考慮せず、幼虫・蛹・成虫という三段階の生活史を持つときの最適エネルギー配分を最適制御理論によって求めた。その結果、幼虫期のある時点から成虫組織の成長率を加速させることが最適な成長戦略であることがわかった。これは実験的に観察される成虫組織の成長パターンと良く一致する。よって、臨界サイズは単に変態のためのチェックポイントであるだけでなく、最適なエネルギー配分切替のためのマイルストーンとして機能していると予想される。
この理論を実験的に検証するため、ショウジョウバエ属昆虫9種を用いて、臨界サイズの到達タイミングと理論的に予測される最適タイミングを比較した。興味深いことに、種間で成虫サイズが三倍以上変動するにもかかわらず、いずれの種においても臨界サイズの到達タイミングは最適に近い値を採っていることがわかった。以上の結果から、完全変態昆虫は臨界サイズにおけるエネルギー配分切替によって最適な成長スケジュールを実現していると考えられる。
現在、個体発育の進行に伴って代謝応答が変化する現象を理解するべく、確率動的計画法を用いたモデリングに取り組んでいる。最適制御理論は従来より進化生態学で用いられてきた手法であるが、発生学や生理学においても、生命現象の設計原理を理解するために有効な手法であると考えられる。